
日本税制研究所

FAX:03-5282-7059
E-mail:jimukyoku@zeiseiken.or.jp


※T&Amaster(ロータス21)2011.1.31 No.388 に掲載
1.外国子会社合算税制の適用手順等の確認
租税特別措置法66条の6(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)等に定められている外国子会社合算税制に関しては、概ね次のような手順で確認と検討を行って適用することとなります。
まず、外国法人の発行済株式又は出資(その外国法人が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額(以下、「発行済株式等」といいます。)の50%超が内国法人や日本の居住者などによって保有されているかどうかを確認することとなります。この確認の結果、発行済株式等の50%超を内国法人等に保有されているということになれば、その外国法人は「外国関係会社」(措法66の6②一)とされることになります。
次に、外国関係会社に該当するその外国法人の本店所在地国における租税負担割合を確認することとなりますが、その外国法人の所得に対して課される租税が存在しないか又は租税負担割合が20%以下である場合には、その外国法人は「特定外国子会社等」とされることになります(措法66の6①、措令39の14①)。
外国法人が特定外国子会社等に該当するということになると、次に、外国子会社合算税制の適用除外の要件に該当するのか否かを検討することとなります。そして、この適用除外に該当しないということになると、その外国法人の所得の全部又は一部がその内国法人の保有する株式又は出資(以下、「株式等」といいます。)の割合に応じて所得に合算されることになります。
外国子会社合算税制は、基本的には、このような手順で検討を行って適用されることとなるわけですが、実際に個別のケースに適用するということになると、上記の判定の時期を確認したり、外国法人の所得が生ずる事業年度とそれを合算する内国法人の事業年度との対応関係を確認するなど、更に細かな作業が必要となります。
(1)外国関係会社・特定外国子会社等に該当するのか否かの判定の時期
内国法人が株式等を保有する外国法人が外国関係会社に該当するのか否かの判定は、その外国法人の各事業年度終了の時の現況により行うこととされています(措法66の9、措令39の20①)。
例えば、X1年12月31日を事業年度末日とする外国法人であれば、その外国法人が外国関係会社に該当するのか否かは、X1年12月31日の時点での資本関係を確認することによって行うこととなります。
その確認の結果、外国関係会社に該当するということになれば、次に、X1年12月31日に終了する事業年度のその外国法人の租税負担割合の確認を行い、特定外国子会社等に該当するのか否かを判定することとなります。
(2)外国法人の事業年度と内国法人の事業年度の対応関係
外国子会社合算税制の適用対象となる特定外国子会社等に該当するとされた外国法人については、各事業年度の所得をその事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む内国法人の各事業年度の所得に合算するものとされています(措法66の6①)。
上記(1)の例を用いて説明すると、内国法人の事業年度が3月31日を末日とする事業年度である場合に、外国法人のX1年12月31日に終了する事業年度の所得が合算の対象となるときは、X1年12月31日の翌日から2月を経過する日、すなわち、X2年2月28日を含む内国法人の事業年度(X2年3月31日終了事業年度)の所得に合算することとなります(図1参照)。
【図1】外国法人及び内国法人の事業年度の対応関係
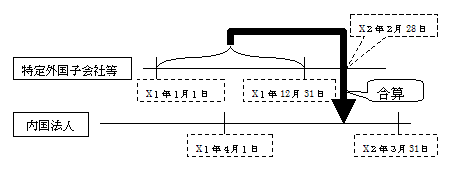
ところで、内国法人が外国法人の各事業年度終了の日以後2月を経過する日までの間に合併により解散した場合に関しては、その内国法人が保有するその外国法人の株式等で合併法人に引き継がれたものは、その合併法人がその外国法人の各事業年度終了の日において保有する株式等とみなす措置が講じられています(措法66の9、措令39の20②)。
【図2】外国法人及び内国法人の事業年度の対応関係
(内国法人が合併により解散した場合)
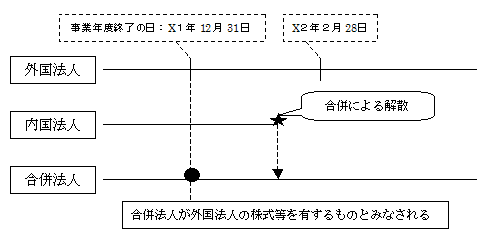
上記の例で説明すると、被合併法人である内国法人がX2年1月31日に合併により解散し、その内国法人の資産及び負債のすべてが合併法人である内国法人に包括承継された場合には、被合併法人である内国法人は、X2年2月28日には存在せず、外国子会社合算税制の適用を受けることはあり得ませんので、合併法人である内国法人を外国子会社合算税制の適用対象とするべく、このような措置が講じられていると考えられます(図2参照)。
2.外国関係会社の株式等を保有する内国法人が解散する場合の留意点
上記1の外国子会社合算税制の適用手順等を踏まえて、外国法人の事業年度終了の日以後2月を経過する日までの間に、内国法人が、合併による解散ではなく、通常の解散を行い、その内国法人の残余財産が確定し、その内国法人の株式等の100%を保有していた他の内国法人である親法人に対してその外国法人の株式等を含む資産が分配された場合に、税制上の取扱いがどうなるのか、ということについて検討してみます。
(1)法人税法62条の5の取扱い
内国法人が通常の解散を行って残余財産の分配を行うということになると、まず、平成22年度改正において新たに創設された法人税法62条の5(現物分配による資産の譲渡)の規定の適用関係がどうなるのかということが問題となります。
これについては、法人税法62条の5の1項及び2項において、内国法人が通常の解散を行って残余財産の分配を行う場合には、その残余財産を時価によって譲渡したものとするとされており、その譲渡利益額又は譲渡損失額は残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入するものとされています。
しかし、その残余財産の分配が「適格現物分配」(法法2十二の十五)に該当する場合には、法人税法62条の5の3項により、残余財産の分配を行う法人(現物分配法人)は、外国法人の株式等を帳簿価額によって譲渡したものとされることとなり、その結果、外国法人の株式等の譲渡損益の計上が繰り延べられることとなります。そして、その外国法人の株式等の分配を受ける内国法人(被現物分配法人)は、法人税法62条の5の4項により、その外国法人の株式等を含む資産の移転を受けたことによって生ずる収益の額を益金の額に算入しないこととされています。
この適格現物分配に該当するのか否かということは、法人税法2条(定義)の12号の15によって判定することとなるわけですが、実際に外国子会社合算税制の適用を受けるケースに関しては、内国法人が直接又は間接に外国法人の株式等の100%を保有していることが多いため、適格現物分配に該当することとなるものが多くなると想定されます。
(2)租税特別措置法66条の6等の取扱い
次に、租税特別措置法66条の6等の外国子会社合算税制における取扱いがどうなるのかということが問題となります。
これに関しては、平成22年度改正による清算所得に対する課税の廃止の前後の取扱いを比較することによって、より一層、理解を深めることが出来ます。
① 平成22年度改正前の取扱い
平成22年度改正前は、通常の解散を行って清算する内国法人については、各事業年度の所得に対する課税ではなく、残余財産の価額(時価純資産価額)から解散時の簿価純資産の価額を控除して得られる清算所得に対する課税が行われており、このような財産法による課税の仕組みの下では、その清算する内国法人とその株主等のいずれにおいても、株式等を保有している外国法人に生ずる所得を自らの所得に取り込んで課税を行うといったことは、行われていませんでした。
しかし、この清算所得課税の下でも、清算する内国法人が株式等を保有している外国法人の所得に対する課税が行われないというわけではなく、その株式等を保有している外国法人に所得がある場合には、それがその清算する内国法人の残余財産の価値を増加させることよって清算所得を増加させることとなり、事実上、その株式等を保有している外国法人の所得に対する課税が行われることとなっていました。
② 平成22年度改正以後の取扱い
平成22年度改正においては、既に述べたとおり、通常の解散を行って清算する内国法人については、清算所得に対する法人税を課すのではなく、残余財産の確定の日までの所得に対して各事業年度の所得に対する法人税を課することとされたため、解散の日の翌日から残余財産の確定の日までの期間内にその内国法人が株式等を保有している外国法人の事業年度終了の日以後2月を経過する日がある場合には、租税特別措置法66条の6等の外国子会社合算税制の適用を受けることがあり得ることとなります。
この点は、平成22年度改正前と異なっていますので、注意が必要となります。
内国法人が株式等を保有している外国法人の事業年度終了の日以後2月を経過する日がその内国法人の残余財産の確定の日の後となる場合には、租税特別措置法66条の6等に外国子会社合算税制を適用するための特別な定めは設けられていませんので、外国子会社合算税制の適用はないこととなります。
この点に関しては、平成22年度改正前と同様となっています。
しかし、平成22年度改正により、同改正前の清算所得に対する課税が各事業年度の所得に対する課税に変更され、また、残余財産の分配が適格現物分配となるものと適格現物分配とならないものに分けられたことにより、課税関係が同正と異なることとっています
通常の散行って清算する内国法人の残余財産の分配が適格現物分配とならない場合には、上記(1)において述べたとおり、外国法人の株式等を含む残余財産を時価によって譲渡したものとされるため、平成22年度改正前の清算所得に対する課税の場合と同様に、事実上、その株式等を保有している外国法人の所得に対する課税が行われることとなります。
他方、通常の解散を行って清算する内国法人の残余財産の分配が適格現物分配となる場合には、外国法人の株式等を含む残余財産を帳簿価額によって譲渡したものとされるため、この内国法人においては、その株式等を保有している外国法人の所得に対する課税は行われないこととなります。
また、適格現物分配によって残余財産の分配を受ける内国法人においても、その外国法人の株式等を含む資産の移転を受けたことによって生ずる収益の額を益金の額に算入しないこととされていますので、やはり、その外国法人の所得に対する課税は行われないこととなります。
外国法人が外国子会社合算税制の適用対象となる可能性のある外国関係会社に該当するのか否かの判定はその外国法人の各事業年度終了の時の現況によることとされていますので(措令39の20①)、 その残余財産の分配を受ける内国法人が外国法人の事業年度終了の時にその外国法人の株式等を保有していない場合のその外国法人の事業年度の所得に関しては、その残余財産の分配を受ける内国法人において外国子会社合算税制の適用を受けることはありません。
要するに、残余財産の分配が適格現物分配に該当することとなる場合には、外国法人の各事業年度分の所得に対する課税が、一部、抜けてしまうことがある、ということになります。
内国法人が通常の解散を行って残余財産の分配を行うというケースにおいて、仮に、外国法人の一事業年度分の所得に対する外国子会社合算税制の適用がないということになると、税負担が大きく軽減されることとなることがあり得ます。
ところで、上記1(2)の後段において取扱いを紹介しましたが、外国法人の株式等を保有する内国法人が合併により解散する場合の取扱いに目を向けてみると、次のような定めが設けられており、上記のような問題は生じないこととなっています。
「2 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が当該内国法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の日以後二月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その有する当該外国関係会社の同条第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等の数(以下この項において「直接及び間接保有の株式等の数」という。)でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人が当該外国関係会社の各事業年度終了の日において有する直接及び間接保有の株式等の数とみなす。」(措令39の20②)
平成22年度改正においては、残余財産の分配を含めて現物分配(法法2十二の六)を組織再編成の一部に加え、適格現物分配に関しては、移転する資産の譲渡損益の計上を繰り延べることとしています。このように、本来は資本等取引である現物分配を組織再編成として税制措置を講ずることの適否は措くとしても、この平成22年度改正により、通常の解散に係る税制上の取扱いが合併に係る税制上の取扱いに非常に近いものとなったことは事実です。そのような中にあって、上記のように、外国子会社合算税制における両者の取扱いには大きな相違があるという状態となっていますので、実務においては、このような相違があることに十分に留意しておく必要があります。