
日本税制研究所

FAX:03-5282-7059
E-mail:jimukyoku@zeiseiken.or.jp


※T&Amaster(ロータス21)2011.2.28 No.392 に掲載
1. はじめに
租税特別措置法66条の6(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の1項においては、税負担が著しく低い外国関係会社(注)を「特定外国子会社等」と呼び、これに外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)を適用するとされていますが、この特定外国子会社等がどのような法人であるのかということに関しては、租税特別措置法施行令39条の14(特定外国子会社等の範囲)に具体的な定めが置かれています。
(注)「外国関係会社」とは、内国法人等が発行済株式等の50%超を有する外国法人とされています(措法66の6②一)。
本稿においては、この租税特別措置法施行令39条の14において、外国法人が他の国に支店を有し、その支店がその所在地国で所得に対する租税を課されていた場合に、どのようにして特定外国子会社等に該当するのか否かの判定を行うこととなるのかということについて、解説を行うこととします。
2. 特定外国子会社等の判定に関する法令の定め
租税特別措置法施行令39条の14第1項においては、次の外国関係会社が特定外国子会社等となるとされています。
① 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社(措令39の14①一)(注)
(注)我が国の税法においては、本店所在地主義(設立準拠法主義)を採っているため、「本店又は主たる事務所の所在する国」とは、その法人が設立に際し準拠した法令の施行地が、その本店所在地国であるということになる、とされています(高橋元監修『タックス・ヘイブン対策税制の解説』118頁、清文社、昭和54年)。
② その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の20%以下である外国関係会社(措令39の14①二)
そして、この上記②の外国関係会社に該当するのか否かの判定においては、「所得の金額」と「租税の額」は、それぞれ次に定めるところによるものとされています。
ⅰ 上記②の「所得の金額」(措令39の14②一)
本店所在地国の外国法人税(法人税法69条1項に規定する外国法人税をいう。)に関する法令の規定により計算した所得の金額に一定の調整を加えた金額
ⅱ 上記②の「租税の額」(措令39の14②二)
次の金額の合計額
イ 本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(本店所在地国の法令により納付したものとみなして控除されるものを含み、一定のものを除く。)
ロ 本店所在地国において減免された外国法人税の額で、租税条約の規定により納付したものとみなされるもの
3. 上記2①の外国関係会社が支店所在地国で税を支払っている場合の取扱い
外国関係会社の本店所在地国において法人の所得に対する税が存在しなかった場合には、その外国関係会社は、上記2①の外国関係会社に該当することとなります。
しかし、この法人の所得に対する税が存在しない国に本店を有する外国関係会社が他の国に支店を有し、その支店所在地国において法人の所得に対する税を課されていた場合(図参照)にも、この外国関係会社は上記2①の外国関係会社に該当することとなるのかという疑問が生じてきます。
【図】
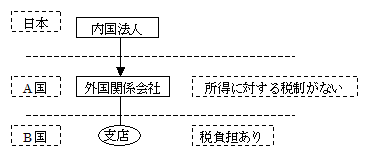
外国関係会社は、本店所在地国では所得に対する税を課されていなかったとしても、支店所在地国では所得に対して高額な税を課されることとなっており、その外国関係会社の全世界の所得の金額に対する税の割合が非常に高くなっている、ということもあり得るわけです。
これに関しては、租税特別措置法施行令39条の14において、上記2①の外国関係会社が他国に支店等を設けている場合の特別な取扱いが定められているわけではありませんので、法令の規定の正しい解釈という点からすると、支店所在地国における所得に対する税の有無にかかわらず、法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する限り、上記2①の外国関係会社に該当することとなる、ということになります。
また、この上記2①の外国関係会社を外国子会社合算税制の適用対象とするという仕組みは、外国子会社合算税制の創設当初からあるため、その創設当初において、上記のような疑問点に対してどのような考え方が採られていたのかとういうことを確認してみると、次のように述べられています。
「 また、外国関係会社の税負担の合計が25%以上であるような場合であっても、その外国関係会社が上述の意味での軽課税国等に所在する場合には、本税制の適用による課税を受けます。例えば、バハマ(法人所得に関する税制が存在しない。)にある外国関係会社が米国源泉の利子を取得し、米国において35%の所得税の源泉徴収を受けたためにその外国関係会社の税負担が全体として25%以上となったとしても、本税制による課税を受けます。このように外国関係会社が軽課税国に所在する場合には、個々の会社の実際の税負担を考慮することなく一律に本税制の対象としています。」(『昭和53年 改正税法のすべて』159・160頁)
この記述からも分かるとおり、外国子会社合算税制の創設当初は、外国関係会社の本店所在地国に所得に対する税制がないということであれば、実際にどのように税負担を行っていたとしても、その実際の税負担は考慮せず、外国子会社合算税制の適用対象とする、という考え方が採られていたわけです。
外国子会社合算税制に関しては、昭和53年の創設以後、数次の改正を経て現在のような規定となっているわけですが、その創設の後の改正において、上記2①の外国関係会社に関する上記の取扱いを改めなければならない事情が生じたということもない、と考えられます。
以上のような点からすると、外国関係会社の本店所在地国に所得に対する税が無いということであれば、実際にどのように支店所在地国において所得に対する税を負担していたとしても、その税負担は考慮されず、外国子会社合算税制の適用対象となる、ということにならざるを得ません。
4. 上記2②の外国関係会社が支店所在地国で税を支払っている場合の取扱い
外国関係会社の本店所在地国において法人の所得に対する税が僅かでも存在する場合には、その外国関係会社は、上記2①の外国関係会社には該当しないこととなり、上記2②の外国関係会社に該当するのか否かということを検討することとなりますが、この上記2②の外国関係会社に該当するのか否かの判定は、所得に対して課される租税の額が20%以下であるのか否かによることとなります。
そして、この場合の「所得の金額」に関しては、上記2②ⅰに記載したとおり、外国関係会社の本店所在地国の外国法人税に関する法令の規定により計算した所得の金額に一定の調整を加えた金額とされていますので、その本店所在地国が我が国のように全世界所得に対して課税を行うという仕組みを採っている場合には、その外国関係会社が他の国の支店で稼得した所得の金額も含むこととなります。
また、上記の「租税の額」に関しては、上記2②ⅱイに記載したとおり、本店所在地国以外の国において課される外国法人税の額を含むとされていますので、外国関係会社が支店所在地国で課される外国法人税の額がある場合には、これを含むこととなります。
このため、外国関係会社が他の国に支店を有し、その支店所在地国において所得に対する税を課されているという場合には、本店所在地国における所得の金額と外国法人税の額にそれぞれ支店所在地国における所得の金額と外国法人税の額とを加えた金額により、上記2②の20%以下であるのか否かということを判定することとなります。
このようにして判定を行うということになれば、本店所在地国における課税が低率であっても、支店所在地国における課税が高率であり、全体として見れば、所得に対して20%超の税を負担しているという外国関係会社が外国子会社合算税制の適用を受けるといった事態は生じないこととなります。
5. 外国関係会社が支店所在地国で税を支払っている場合の留意点
上記3及び4において述べたとおり、現行法令上は、外国関係会社の本店所在地国において所得に対する税があるのか否かによって外国子会社合算税制の適用対象となるのか否かの判定方法が大きく異なることとなっているため、海外進出に当たって外国法人が他の国に支店等を有する状態となる場合には、この点に十分に留意する必要があります。
ただし、外国子会社合算税制の制度の本来のあり方という点からすると、租税特別措置法施行令39条の14第1項1号の定めの要否に関しては改めて検討を行う余地があるように思われます。
上記2②は、平成4年度改正において、従来の軽課税国指定制度を廃止して新たに設けられたものですが、同改正前においても無課税国と軽課税国とを分けるという考え方は採られていなかったわけですから、同改正において無課税国と軽課税国とを分けることとした理由が何かという疑問が生じてきます。しかし、平成4年度改正に関して、特にこの点に言及した解説等は見当たりません。本店所在地国が無課税又は軽課税であれば支店所在地国における課税の如何にかかわらず外国子会社合算税制を適用するという考え方を採るのか、あるいは、現に無課税又は軽課税となっている場合に外国子会社合算税制を適用するという考え方を採るのかという問題は現在も残ったままとなっていると言ってよいでしょう。
最後に、国際的な動向を知る上で最も参考となると考らるOECD租税委員会における「ックス・ヘイブン」の義(注)を紹介しておくこととします。
(注)HARMFUL TAX COMPETITION AN EMRGING GLOBAL ISSUE, pp.22-25
OECD租税委員会では、次の①に該当し、かつ、次の②から④までのいずれかに該当する場合には、その国又は地域を「タックス・ヘイブン」とするとしています。
① 金融・サービス所得に対する課税がない、又は当該所得に対して名目的な課税しかない
② 他国との間で納税者に関する有効な情報交換を行っていないこと
③ 税制を含めた法制度及び法慣習において透明性が欠如していること
④ その国で行われる企業活動について実体性を必要としないこと
この定義からは、単純に所得に対する税が存在しない国又は地域を「タックス・ヘイブン」とするのではなく、租税に関する必要な情報を公開しない又は企業活動に実体性を求めない国又は地域が、国際租税上、非難されるべき「タックス・ヘイブン」と認定されるべきであるという考え方を窺い知ることができます。
国際社会からタックス・ヘイブンに対して厳しい目が向けられる状況の中で、この定義に該当する軽課税国では、その税制を見直す国又は地域も現れてきており、我が国が租税協定を締結したバミューダ(平成22年2月署名済み)や、ケイマン諸島(平成23年2月署名済み)もその一例と言ってよいと考えます。