
日本税制研究所

FAX:03-5282-7059
E-mail:jimukyoku@zeiseiken.or.jp


※T&Amaster(ロータス21)2011.4.11 No.398 に掲載
1.基準所得金額の計算
外国子会社合算税制の対象となる内国法人に係る特定外国子会社等が合算課税の適用除外要件を満たさない場合には、その特定外国子会社等の所得の金額のうちその内国法人の持分割合に応じた金額がその内国法人の所得の金額に合算されることとなります。本稿においては、この合算課税の適用の基礎となる特定外国子会社等の適用対象金額について、その概要を確認し、実務上の留意点について解説を行うこととします。
この特定外国子会社等の適用対象金額は、特定外国子会社等の各事業年度の基準所得金額を基礎として、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額とされています(措法66の6②二)。(図参照)
【図】適用対象金額の計算過程のイメージ図
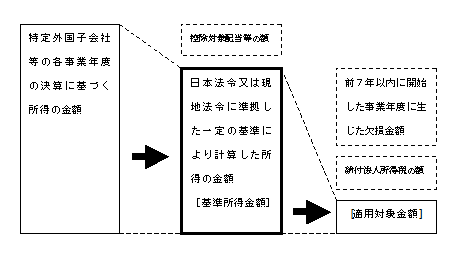
この特定外国子会社等の適用対象金額の計算の基礎となる基準所得金額とは、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及び租税特別措置法による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして一定の基準により計算されます(措法66の6②二)。
ただし、この基準所得金額に関しては、このように日本の法令に準拠して計算することを原則としながらも、特定外国子会社等の現地の法令に準拠して計算することも認められています(措令39の15①・②)。
(1)日本法令に準拠して計算する方法
日本法令に準拠して計算する場合には、基準所得金額は、次のイ及びロに掲げる金額の合計額からハ及びニに掲げる金額の合計額を控除した残額とされています(措令39の15①)。
イ 特定外国子会社等の各事業年度の決算所得金額について、日本の法人税法等の規定に準じて計算した所得の金額又は欠損の金額(措令39の15①一)
ロ 各事業年度において納付する法人所得税の額(同二)
ハ 各事業年度において還付を受ける法人所得税の額(同三)
ニ 各事業年度において子会社から受ける配当等の額(同四)
上記イは、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、次の(イ)及び(ロ)に掲げる規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額とされています(措令39の15①一)。
(イ)法人税法第2編第1章第1節第2款~第9款、第11款の規定で、23条等の規定を除い
たもの
(ロ)租税特別措置法43条、45条の2、52条の2、57条の5、57条の6、57条の8、57条の
10、61条の4、65条の7(1項の表の19号に係る部分に限ります。)、65条の8(65条の
7に規定する資産に係る部分に限ります。)、65条の9(65条の7に規定する資産に係る
部分に限ります。)、66条の4第3項、67条の12、67条の13
(2)現地法令に準拠して計算する方法
現地法令に準拠して計算する場合には、基準所得金額は、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その特定外国子会社等の本店所在地である現地の法人所得税に関する法令の規定により計算した所得の金額に、その現地の法令の規定により課税標準に含まれないこととされる所得の金額等を加算し、一定の金額を控除した残額とされています(措令39の15②)。
2 準拠法令の相違による基準所得金額の著しい乖離の容認の可否
上記のとおり、基準所得金額は日本法令に準拠して計算することを原則としながら特例として現地法令に準拠して計算することも認めることとされているわけですが、例えば、日本法令に準拠して計算した場合には基準所得金額が非常に大きな金額となるものの、現地法令に準拠して計算した場合には基準所得金額が非常に小さな金額に留まるといったことも有り得ます。このような場合には、現地法令に準拠して計算することで問題はないのかという疑問が生じてくることがあるものと考えられます。
この点についてもう少し具体的な例で考えてみたいと思いますが、次のような例がその一例となります。
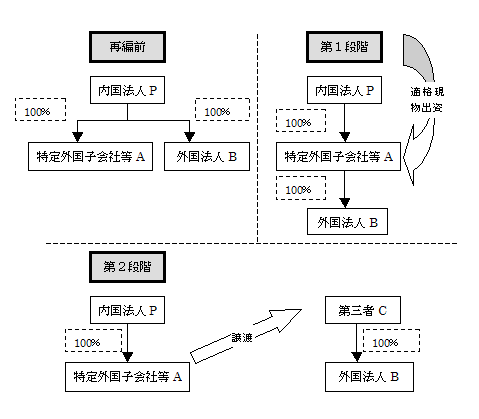
(注1)外国法人Bの株式の時価は300、内国法人Pにおける税務上の簿価は100とします。
(注2)すべての段階において外国法人Bの株式の時価は変動しないものとします。
(注3)特定外国子会等Aの本店所在地国の現地法令により、現物出資により受け入れた資産の価額は受入れ時の価額(すなわち、時価)とされており、出資者におけるその資産の帳簿価額とはされていないとします。
(注4)特定外国子会社等Aの本店所在地国の現地法令により、一定の株式の譲渡益は非課税扱いとされるものとします。
この例では、第1段階において、内国法人Pは、その有する外国法人Bの株式の全部を適格現物出資(法法2十二の十四イ、法令4の2⑨・⑩)に該当する現物出資によって特定外国子会社等Aに移転します。この適格現物出資による移転によって、内国法人Pは外国法人Bの株式の譲渡益200(=300-100)について税制上で課税の繰延べの適用を受けます(法法62の4①)。
第2段階では、特定外国子会社等Aは、外国法人Bの株式の全部を第三者であるCに譲渡することになりますが、この譲渡による譲渡益の金額について、日本法令に準拠する方法と現地法令に準拠する方法のいずれに拠って特定外国子会社等Aの基準所得金額を計算するのかということが問題となることになります。
まず、日本法令に準拠して計算する場合には、特定外国子会社等Aが取得する外国法人Bの株式の日本の税制上の取得価額は100となり(法法62の4②、法令123の5)、第三者Cに対する譲渡により譲渡益は200(=300-100)となり、基準所得金額は200となります。
他方、現地法令に準拠して計算する場合には、現地の税制上、特定外国子会社等Aの外国法人Bの株式の取得価額が受入れ時の時価とされていることから、現地法令に準拠して計算される第三者Cに対する譲渡により生ずる譲渡益は0(=300-300)となります。現地法令に準拠して基準所得金額の計算をする場合、現地法令における課税所得金額には、現地法令による非課税所得金額を加算することになりますが、この例の場合には、そもそも現地法令による非課税所得金額が発生しませんので、加算する金額はないこととなります。
このように、日本法令と現地法令のいずれに準拠して計算をするのかによって、基準所得金額が大きく異なることがあり、このような場合に、特例である現地法令に準拠して基準所得金額を計算することには弊害がある、といったような話にならないのかという疑問が生ずることとなるわけです。
これに関しては、租税特別措置法施行令には、基準所得金額の準拠法令について、継続適用の制限はあるものの、このような場合に、特に準拠法令を制限する旨の定めは設けられていませんので、法令の規定を文理解釈する限り、現地法令に準拠して計算し、基準所得金額を0としてよい、ということになります。
念のため、外国子会社合算税制の創設時の基準所得金額の計算の準拠法令に関する部分の考え方を確認してみると、次のように述べられています。
「 本税制が特定外国子会社の留保所得の内国法人への帰属というシステムを採っている以上、その合算の基礎となる金額の計算は原則として我が国税法の所得計算の基準に従って統一的に行うことが望ましいわけです。この考え方に立ち、本税制は、特定外国子会社等の所得を原則的に我が国の法人税法及び租税特別措置法の規定の例に準じて計算することとしています。しかしながら特定外国子会社の所在地国の税に関する法令による所得計算であっても、一定の調整(例えば国外源泉所得が課税所得に含まれないような税制の国の場合にそれを未処分所得の金額に含める。)を加えればそれによることも可能とされました。これは、納税義務者が我が国の法令に従って所得を再計算することが過重な負担になるかもしれないことを考慮し、納税者の便宜のために設けられたものです。なお、一度準拠した法令を他の法令に変更しようとするときは、あらかじめ所轄税務署長の承認を受けることが必要とされています(措令25の9⑥、39の14⑥)。」(『昭和53年 改正税法のすべて』161頁)
この記述からすると、基準所得金額の計算における準拠法令の原則と特例の選択に関しては、その計算の結果に大きな相違があったとしても、特にそれに制限を加えるという考え方は存在していない、と解してよいと考えられます。
3 準拠法令の変更の可否
この基準所得金額の計算における準拠法令に関しては、変更の可否にも疑問が生ずることがあると考えられます。
上記2の例においては、仮に、内国法人Pが特定外国子会社等Aの基準所得金額の計算に関して外国法令に準拠することを選択していなかったとすれば、多額の合算課税が生ずることとならざるを得ません。
このため、内国法人Pは、上記ののような取引が生ずることが想定された場合には、基準所得金額の計算の準拠法令を現地法令に変更することができるのであれば、そのようにしたいと考えるはずです。納税者としては、当然、何とか有利な結果となる取扱いを選択することができないかと考えるはずであり、それに対する答も用意しておく必要があると考えます。
この基準所得金額の計算における準拠法令の変更に関しては、租税特別措置法施行令39条の15第9項に、あらかじめ所轄税務署長の承認を要する旨の定めがあるのみで、それ以上の具体的な判断の拠り所となるものは存在していないものと思われます。このため、これに関する検討を深めることは、容易ではありません。
ところで、所得の金額を計算する場面においては、この基準所得金額の計算における準拠法令だけでなく、複数の計算方法が用意されてその変更が認められているものがいくつか存在していますが、法人税法施行令30条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)及び同条3項の解釈を示した法人税基本通達5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)や同令52条(減価償却資産の償却の方法の変更手続)及び同条3項の解釈を示した同通達7-2-4(償却方法の変更申請があった場合の「相当期間」)などはその典型的な例となります。
法人税法施行令30条や52条は、租税特別措置法施行令39条の15第9項とは異なり、「相当期間を経過していないとき」や「計算が適正に行われ難いと認めるとき」には方法の変更を認めないとしており、これらの定めを受けて、法人税基本通達5-2-13や7-2-4においては、「3年を経過していないとき」や「合理的な理由がないと認められるとき」は変更を承認しないことができる、としています。
また、棚卸資産の評価方法等の変更の可否が問題となった例はあまり多くはないと考えられますが、昭和63年の高裁判決においては「法人税法は、法人が棚卸資産の評価方法を令所定のものから選定することは許しつつも、その変更については極めて慎重な態度をとっているといえ、これは、経理処理の継続性を図り、できる限り毎期の評価方法を同一にして利益計算の一貫性を確保しようとするもので、会計処理の原則の一つである継続性の原則を重視するとともに、反面、安易な評価方法の変更によつて法人による恣意的な利益操作がなされることを排除しようとしたものと解される。」(昭和63年3月31日大阪高裁61(行コ)32・33)としています。
租税特別措置法の規定は法人税法の規定よりも詳細に定められるのが通例であることや、租税特別措置法施行令39条の15第9項は変更の事前承認が必要であるということを定めるのみで法人税法施行令30条や52条のように「相当期間を経過していないとき」と「計算が適正に行われ難いと認めるとき」に方法の変更を認めないということとはされていないことからすると、法人税法施行令30条や52条のような解釈をそのまま採ることはできないと考えられますが、変更を税務署長の承認事項としていることからすると、上記の高裁判決にもあるとおり、恣意的な利益操作は認めない、という観点は、租税特別措置法施行令39条の15第9項にも存在すると考えられます。
法人税法施行令30条や52条のようには厳格ではなく、しかし、恣意的な利益操作は認めない、というものが、具体的にどのようなものであるのかということは、必ずしも明確ではありませんが、基準所得金額の計算における準拠法令の変更に関しては、上記のような状況にあることを理解した上で、変更申請を行い、また、変更申請の検討や税務調査における可否の判断を行う必要があると考えます。