
日本税制研究所

FAX:03-5282-7059
E-mail:jimukyoku@zeiseiken.or.jp


平成20年度改正で法人税法施行令131条の2(リース取引の範囲)の2項の規定に「当該資産を事業の用に供するために要する費用の額を含む。」という括弧書きが追加されましたが、この改正は、法人税法64条の2の規定と同様に、「平成20年4月1日以後締結される契約に係るリース取引」について適用されると考えてよろしいでしょうか。
法人税におけるフルペイアウトの形式的要件は、従来、旧法人税基本通達12の5-1-2(資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきことの意義)に示されていましたが、平成19年度改正により、そのうち、「その資産の取得のために通常要する価額のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合」という文言だけが法人税法施行令131条の2の2項に規定されました。
そして、平成20年度改正により、その括弧書き部分である「当該資産を事業の用に供するために要する費用の額を含む。」という文言が追加されました。
その変遷を図解すると、図表72のとおりとなります。
| 政令(法令131 の2②) | 通達(旧法基通12 の5−1−2) | |
| 平 成 19 年 度 改 正 前 |
(規定なし) | 令第136条の3第3項第2号《リース取引の定義》に規定する「当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこと」とは、その賃貸借期間中に賃借人が支払うリース料の額の合計額が、賃貸人における賃貸借資産の取得価額及びその取引に係る付随費用(賃貸借資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。以下12の5-1-3において同じ。)の額の合計額のおおむね全部(原則として100分の90以上)とされていることをいう。 |
| 平 成 19 年 度 改 正 |
資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法第六十四条の二第三項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。 | (廃止) |
| 平 成 20 年 度 改 正 |
資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産を事業の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法第六十四条の二第三項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。 | (廃止) |
ここで問題となるのは、平成20年度改正により追加された括弧書き部分の適用時期が、旧法人税基本通達12の5−1−2の廃止と平成19年度改正による法人税法施行令131条の2の2項の規定の適用時期と異なっているという点です。
旧法人税基本通達12の5−1−2は、平成20年4月1日前4に締結される契約に係るリース取引について適用され(平成19年改正法基通附則「35経過的取扱い」の(経過的取扱い…リース取引に係る改正通達の適用時期))、平成19年度改正による旧法人税法施行令131条の2の2項の規定は、平成20年4月1日以後44に締結される契約について適用されます(平成19年改正法附則44、平成19年改正法令附則1二)。
したがって、両者には連続性があります。
法人税基本通達附則(経過的取扱い:リース取引に係る改正通達の適用時期
この法令解釈通達による改正後の(中略)12の5−1−1から12の5−1−3まで(中略)の取扱いは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る法第64条の2第3項《リース取引の範囲》に規定するリース取引について適用し、同日前に締結された契約に係る法人税法施行例の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)による改正前の令第136条の3第3項《リース取引の範囲》に規定するリース取引については、なお従前の例による。
平成19年度改正法附則44条:リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過処置
新法人税法第六十四条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。
平成19年度改正法令附則1条(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 省 略
二 (前略)第二編第一章第一節第三款の次に二款を加える改正規定(第三款の二に係る部分に限る。)、(中略) 平成二十年四月一日
しかし、平成20年度改正による法人税法施行令131条の2の2項の規定の改 正は、平成20年改正法令附則において別段の定めがないことから、経過措置の原則に基づき、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されます(平成20年改正法令附則2)。
平成20年改正法令附則2条(経過処置の原則)
別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下『新令」という。)の規定は、法人(中略)の平成二十年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税(中略)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税(中略)については、なお従前の例による。
例えば、平成19年5月1日から平成20年4月30日までの事業年度における法人は、平成20年4月1日から4月30日までに締結された契約に係るリース取引については、旧法人税法施行令131条の2の2項の規定が適用されるのに対して、平成20年度改正によって法人税法施行令131条の2の2項に追加された括弧書き部分の規定は、まだ適用されないこととなります(図表73参照)。
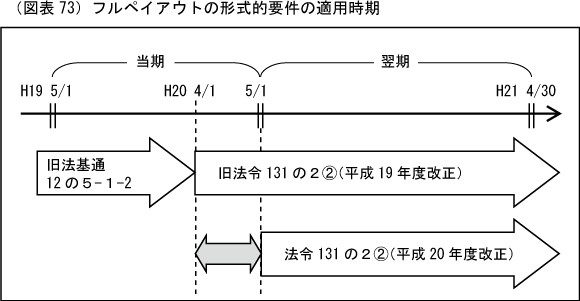
そのため、このような場合においては、平成20年改正法令附則2条(経過措置の原則)に規定する適用関係に従えば、フルペイアウトの形式的要件の判定にあたって、「賃借人が支払う賃借料の金額の合計額」と「資産の取得のために通常要する価額(その資産を事業の用に供するために要する費用の額を含まない金額 )」を比較することにより行わなければならないこととなります。
しかし、そもそも、平成19年度改正により創設された法人税法64条の2の規定は、事業年度の開始時期に関係なく、一律に平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリース取引に適用される(平成19年改正法附則44)ことを勘案すれば、適用関係を異にすることを意図してこのような適用関係にしたとは考え難く、本来であれば、平成20年度改正による法人税法施行令131条の2の2項の規定の括弧書きの部分の適用関係は、附則に経過措置に関する別段の定めを設け、「平成20年4月1日以後締結される契約に係るリース取引について適用する。」とすべきではなかったかと考えられます。
このような事情がありますので、上記のような場合についてどのように取り扱うべきかという問題は大きな難問とならざるを得ないわけですが、税務執行当局が課税を行う場合には法令の根拠に基づいて行わなければなりませんので、上記のようなケースに対しては、納税者が平成20年度改正の部分を規定どおりに平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用するという解釈を行って申告を行った場合に、税務執行当局が平成20年度改正の部分を平成20年4月1日以後に締結される契約から適用するという解釈を採って課税を行うということは許されないものの、納税者が平成20年度改正の部分を平成20年4月1日以後に締結される契約から適用するという解釈を採って申告を行った場合には、税務執行当局はその申告を容認する、という取扱いが妥当ではないかと考えます。
このような事情にある場合にどのような解釈を行うべきかということに対して一概に画一的な答を出すことは出来ないと考えられますが、社会通念からすれば、立法の不備の責めを納税者に負わせることとなる解釈は取り得ないものと考えます。