
日本税制研究所

FAX:03-5282-7059
E-mail:jimukyoku@zeiseiken.or.jp


※T&Amaster(ロータス21)2011.10.17 No.423に掲載
※T&Amaster(ロータス21)2011.11.21 No.427に掲載
現在、当社のグループは、個人株主の甲とその親族が我が国の持株会社Hとシンガポールの事業会社Pの株式のそれぞれ50%超(100%未満)を保有し、このHが我が国の事業会社Aの株式の100%を保有するという状態となっています。
このAの事業は製造業であり、PはAが作った商品の卸売業を営むという関係にあり、双方の事業には密接な関連があるため、Pがこれらの事業の全般を統括して従来以上に一体的で効率的な事業展開を図ることができる体制にしたいと考えています。
このため、三角合併により、Pが我が国に新設会社Bを設立してAを吸収合併し、AをPの100%子会社とし、HがPを経由して間接的にAの株式を保有する、という形態にグループ構成を変更したいと考えています。
しかし、シンガポールにおいて子会社(我が国の新設会社B)が親会社(シンガポールのP)の株式を保有することが許されるのか否かがはっきりしないため、Aが金融機関から100億円の借入れを行い、その100億円をもってPに対する増資を行い、Pはその100億円で我が国にBを設立し、そのBがAを吸収合併したことによってBの資産となったその増資新株を合併対価としてHに交付する、ということとしたいと考えています。
合併対価として交付することを予定しているのは、この増資に係る株式のみです。
Pの所得に対して課される租税の割合は、従来、20%超となっており、今後も同様と見込まれています。
Aが金融機関から借り入れた100億円に関しては、Aを吸収したBに残ることとなりますので、金融機関に対しては、合併後に、Bがその100億円を返済することとする予定です。
当然のことながら、BはAの事業と従業員の全てを引き継ぐこととなり、甲及びその親族とHは、それぞれの保有する株式を継続保有する予定です。
この場合の被合併法人A、合併法人B、被合併法人の株主Hの税制上の取扱いがどうなるのかということをご教授下さい。
要 旨
【マエストロの解説】
1 スキームの概要
本件における増資と三角合併を概要図で示すと、次のとおりとなるものと考えられる。
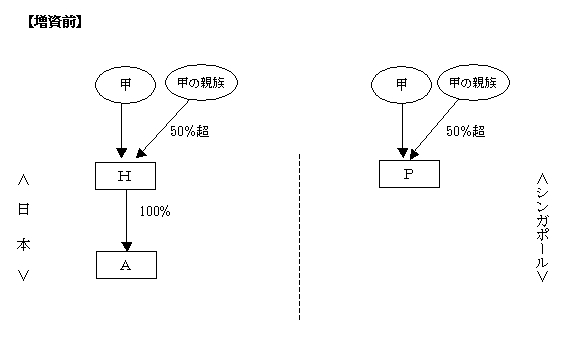
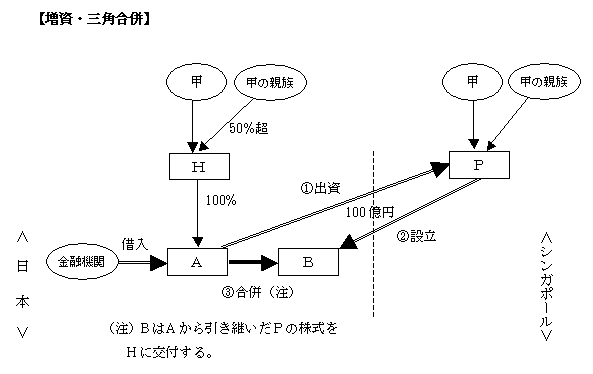

本件の三角合併は、合併法人が被合併法人の株主に合併対価として交付する親法人株式について、合併法人が事前に購入するのではなく、被合併法人が合併直前に増資によって取得するという点が、三角合併の典型的な例として語られるものとは異なっているため、この点に留意しつつ、検討を行うこととする。
ただし、以下の記述に関しては、本件の三角合併が組織再編成に係る行為又は計算の否認の規定(法法132の2)の適用対象とならないという前提に立って行うものであることを予め確認しておくこととする。
本件に関しては、質問文を読む限り、組織再編成に係る行為又は計算の否認の規定の適用対象となることはないものと思われるが、組織再編成の中でも、我が国の資産が国外に流出して我が国の課税権が及ばない事態となるおそれがあるものに対しては、我が国の課税当局が厳しい目を向けることとなるのは、当然である。
このため、クロスボーダーの三角合併に関しては、組織再編成に係る行為又は計算の否認の規定の適用の有無だけでなく、他の要件規定の適用に関しても、他の組織再編成以上に注意を払う必要があると考えられる。
2 スキームの検討
(1)増資
本件に関しては、まず、増資に関する検討が必要となるが、その検討に当たっては、1株当たり金額をどのような金額とするのかということが最も大きな問題となると考えられる。
このため、以下(1)においては、増資における1株当たりの金額に関する取扱いに焦点を当てて検討を行うこととする。
まず、関係法令を確認することとするが、Aが金融機関から100億円を借り入れて行うPに対する増資においては、税制上、Aは、法人税法施行令119条1項2号(金銭の払込み等により取得した有価証券の取得価額)の規定によって処理を行うこととなる。
Pは、外国法人であるため、我が国の法人税法の適用は受けないこととなる。
法人税法施行令119条1項2号の規定においては、金銭の払込みによって取得をした有価証券は、「払込みをした金銭の額」を取得価額とすることとされている。
この「払込みをした金銭の額」とは、現に払い込んだ金額を指し、仮に、時価よりも低い金額を払い込んでも、また、時価よりも高い金額を払い込んでも、現にその払込みをした金額となる。
この法人税法施行令119条1項2号の規定は、株式の発行法人に関して定めた8条1項1号(株式発行等の場合の資本金等の額の増加額)の規定に対応するもので、同号においては、株式を発行した場合には「払い込まれた金銭の額」に相当する金額の資本金等の額を増加させることとされている。
これらの規定は、いずれも平成18年度改正によって改正されたものであり、同改正前は、
次のように定められていた。
<有価証券の取得価額(旧法令119①二)>
「金銭の払込みにより取得をした有価証券(省略) その払い込んだ金額(その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)」
<資本積立金額(旧法法2十七イ)>
「株式(省略)の発行価額のうち資本に組み入れなかつた金額」
平成18年度改正前は、上記の有価証券の取得価額と株式の発行価額は、いずれも適正な金額、すなわち、時価と解されていたが、同改正により、文字どおり、「払い込んだ金額」とすることとされている(注)。
(注)『平成18年度 税制改正の解説』においては、次のとおり、株式の発行等に際して資産の給付を受けた場合に関してはその資産の時価をもって増加させる資本金等の額とすることを明示しつつ、金銭の払込みをした場合の取扱いに関しては会社法を示して説明を行っているが、改めて言うまでもなく、会社法においては、時価を基準にして現に払込みを行っていない金額を含めて資本金の額等を増加させるといったことは行われない。
「 法人が現物出資を受けた場合には、給付を受けた資産の価額(すなわち時価)をもって増加させる資本金等の額とすることとされた」(248頁)
「(注)会社法では、株式について発行価額という概念がなくなり、株主となる者が会社に対して払込み又は給付をした財産の額をもって増加する資本金の額及び資本準備金の額が決定されることとなりました。」(同前)
また、『平成18年度 税制改正の解説』においては、有価証券の取得に関する改正に関しても、次のとおり、会社法の「金銭の払込み」(会203①三他)と同様の取扱いとすることが示唆されている。
「 ここでいう金銭の払込み及び金銭以外の資産の給付とは、募集株式の発行等の手続き(会社法以外の法律によるこれと同様のものを含みます。)による新株の発行又は自己株式の処分によるものを指します。」(279頁)
このように、税制上、時価ではなく、任意の価格によって取引を行い得ることとすることの適否に関しては、異見があると考えられるが、実務においては、その適否とは別に、現に行われた改正に従って対応することが必要となる。
このため、金銭の払込みによって増資を行う限り、株式を取得するAに関しては、その株式の取得の処理について、税制上の問題点が生ずる可能性は少ない、と言ってよい。
しかし、この増資に関しては、いわゆる有利発行に該当しないのか否かということは確認しておく必要がある。
法人税法施行令119条1項4号(有利発行の場合の有価証券の取得価額)においては、払込みをした金銭の額が「払い込むべき金銭の額(省略)を定める時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合」には、有価証券の取得価額は、「その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額」としなければならないとしている。
この「通常要する価額に比して有利な金額」に関しては、法人税基本通達2-3-7(通常要する価額に比して有利な金額)において、「当該株式の払込み又は給付の金額(以下2-3-7において「払込金額等」という。)を決定する日の現況における当該発行法人の株式の価額に比して社会通念上相当と認められる価額を下回る価額をいうものとする」として、次の注記を行っている。
「1 社会通念上相当と認められる価額を下回るかどうかは、当該株式の価額と払込金額等の差額が当該株式の価額のおおむね10%相当額以上であるかどうかにより判定する。」
ところで、この法人税法施行令119条1項4号においては、有価証券の発行が有利発行であると判定された場合にその有価証券の取得価額とするべき金額について、上記引用のとおり、「その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額」としており、この金額に関しては、法人税基本通達2-3-9(通常要する価額に比して有利な金額で新株等が発行された場合における有価証券の価額)において、非上場有価証券の場合には、次のとおりとしている。
「(3)上記(1)及び(2)以外の場合 その新株又は出資の払込期日において当該新株につき4-1-5及び4-1-6《上場有価証券等以外の株式の価額》に準じて合理的に計算される当該払込期日の価額」
この法人税基本通達4-1-5(上場有価証券等以外の株式の価額)と4-1-6(上場有価証券等以外の株式の価額の特例)は、資産の評価益の取扱いについて定めた法人税法25条3項(資産評定における評価益の益金算入)の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があったときの株式の価額について、「当該再生計画認可の決定があった日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額」(法基通4-1-5(1))としたり、「財産評価基本通達(省略)の178から189-7まで《取引相場のない株式の評価》によって算定した価額」(法基通4-1-6)とする特例を認めることとしているものである。
この有利発行に関する法令と通達の取扱いは、昭和48年に定められたものであるが、有利発行に該当するのか否かという判定の時期及び判定の基準となる金額と有利発行に該当した場合の処理の時期及び処理の基準となる金額とが異なるという特徴を有している。
すなわち、有利発行であるのか否かを判定する時期は「払い込むべき金銭の額(省略)を定める時」であり、その判定の基準となる金額は「当該株式の払込み又は給付の金額(以下2-3-7において「払込金額等」という。)を決定する日の現況における当該発行法人の株式の価額」(注)という取引のための価額であるが、この判定によって有利発行に該当すると判定された場合に税制上の処理を行うときのその処理の時期は「その取得の時」であり、その処理の基準となる金額は「当該再生計画認可の決定があった日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額」や「財産評価基本通達(省略)の178から189-7まで《取引相場のない株式の評価》によって算定した価額」という税務の観点から判断したり算出した価額としているわけである。
(注)この金額に関しては、会社法において株式の「発行価額」という概念がなくなったことに伴って行われた平成18年度改正の前までは、「発行価額」とされていた。
有価証券が有利発行に該当したという場合にその有価証券の取得のために通常要する価額を計算するという場面と株式の評価益を計算する場面には、法人税において株式の評価を行うという点で共通性があり、相続税における株式の評価の手法を用いることにも妥当性があると考えられるが、有価証券が有利発行に該当するのか否かという判定においては、そのような税務における評価額ではなく、「発行価額」や「株式の価額」という取引のための価額を用いることとなっている点に留意する必要がある。
このように、有利発行に関して、二つの時期と二つの金額を区別するという創設時の考え方は、法令及び通達を創設時から現在まで変更せずに引き継いでいる(注)ことからすると、現在も変わっていない、ということになる。
(注)平成18年度改正において、有利発行に関して通達に定めていた取扱いを法令(旧法令119①四)に定めることとした際に、有利発行に該当するのか否かを判定する時期を「取得の時」としたが、その翌年の平成19年度改正において、現在のように「払い込むべき金銭の額(省略)を定める時」に改めて、昭和48年の有利発行に関する取扱いの創設時と同様の取扱いに戻している。この平成19年改正は、前年度改正の難点を修正したものであるが、このような事情があるため、厳密に言えば、二つの時期を区別するという点に関しては、1年間だけ途切れた時期が存在する。
本件に関しても、このような点を踏まえて、まず、増資が有利発行に該当しないのか否かということを判定する必要がある。
本件においては、Pの増資に関して、「払い込むべき金銭の額を定める時」において、取引のための価額としての「株式の価額」となる金額がどのような金額であるのかということが分からないため、正確な判定は難しいが、売買実例や第三者評価機関の評価額などに拠ることとすれば、基本的には、有利発行とされることにはならないと考えられる。
なお、有利発行に当たらない場合であっても、払込金額に比して株式を少なく交付するということになれば、増資によって株式を取得した株主とそれ以外の株主との間で株式の価値の移転が生ずることとなるため、株主間の寄附金=受贈益という問題が生ずる可能性がある点には、注意が必要である。
(2)三角合併
本件は、外国法人の株式を合併対価として交付する三角合併であるため、まず、クロスボーダーの組織再編成の取扱いに関する制限措置の適用対象とならないのか否かという点について検討を行う必要がある。
その後に、本件の三角合併が適格合併となるのか否かという点を確認した上で、被合併法人Aにおける取扱い、合併法人Bにおける取扱い、そして、被合併法人の株主Hにおける取扱いを検討することとする。
① クロスボーダー組織再編成の取扱いに関する制限措置の適用の有無の検討
クロスボーダーの組織再編成の取扱いに関する制限措置は、三角合併等を適格合併とする改正に併せて、平成19年度改正により、アメリカに倣って措置されたもので、租税回避が行われることを防止する趣旨の措置と考えてよいものである。
この措置は、次の4つの取扱いから成るものである。
イ 合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例(措法37の14の2、法令188①十七)
ロ 適格合併等の範囲に関する特例(特定の三角合併等の適格性の否認)(措法68の2の3)
ハ 特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例(措法37の14の3、68の3、68の109の2)
ニ 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入(コーポレート・インバージョン対策合算税制)(措法66の9の2~66の9の5)
上記イは、非居住者又は外国法人に対して合併等により外国法人の株式を交付した場合には、将来、我が国で課税を行い得なくなるおそれがあるため、合併等の時点で課税を行っておくこととする趣旨によって措置されたものであり、非居住者又は外国法人が合併等により外国法人の株式の交付を受ける場合にのみ適用される取扱いであることから、内国法人であるHが株式の交付を受けることとなる本件の場合には、検討を行う必要がない。
上記ロは、三角合併等を利用して、経済実態や実質的な株主構成を変えずに、内国法人を外国法人の子会社という状態に変換すること(いわゆる「コーポレート・インバージョン」)により、租税回避を行うことが容易になることが懸念されることから、企業グループ内の内国法人間で行われる一定の三角合併等のうち、軽課税国の外国法人の株式を対価とするものを適格合併等に該当しないものとする趣旨によって措置されたものである。
この措置の適用対象となる合併は、「特定グループ内の合併」(措法68の2の3①)とされており、具体的には、次のとおりとされている。
「 次の各号のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。
一 被合併法人と合併法人との間に特定支配関係があること。
二 被合併法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次項第三号において同じ。)に同条第十二号の八に規定する合併親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)に限る。)が交付されること。」(措法68の2の3①)
この租税特別措置法68条の2の3第1項2号括弧書きの「特定軽課税外国法人」とは、同条5項1号において「その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人をいう」とされており、租税特別措置法施行令39条の34の3第5項においては、次に掲げる法人とされている。
「一 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人
二 法第六十八条の二の三第一項から第四項までの合併、分割、株式交換又は現物出資が行われる日を含むその外国法人の事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度において、その事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十以下であつた外国法人」
本件においては、Pの租税負担割合が20%超となっているとのことであり、Pは「特定軽課税外国法人」に該当しないため、本件は、上記ロの措置の適用対象とはならないこととなる。
上記ハは、非適格合併等の場合に、被合併法人の株主等において旧株式の簿価譲渡による譲渡益課税の繰延べを認めないこととするものであり、国際的租税回避を防止する観点から措置するものと説明されている。
この措置は、合併が適格となる場合には適用されないこととなるため、下記②において述べるとおり適格合併となることが見込まれる本件においては、検討を要しないものと考えられる。
上記ニは、国際的租税回避防止の観点から、コーポレート・インバージョンが行われた場合に、軽課税国における外国法人となっている親会社等の所得を我が国におけるその株主等の所得として合算課税を行うこととする措置である。
この措置は、「特殊関係株主等(省略)が特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(省略)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(省略)を間接に保有する関係として政令で定める関係(省略)がある場合において、当該特関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この項及び第八項において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この条及び次条において「特定外国法人」という。)」(措法66の9の2①)が「適用対象金額」(同前)を有するときに適用されることとなる。
この「政令で定める外国関係法人」に関しては、租税特別措置法施行令39条の20の2第7項において、次に掲げるものとされている。
「一 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係法人(省略)
二 その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十以下である外国関係法人」
本件においては、既に述べたとおり、Pの租税負担割合が20%超となっているとのことであり、Pは上記の「外国関係法人」に該当しないため、本件は、上記ニの措置の適用対象とはならないこととなる。
② 適格判定の検討
本件に関しては、質問文の資本関係を前提とすると、50%超100%未満のグループ内の合併として適格合併になるのか否かということが問題となる。
この適格判定の根拠規定は、法人税法2条12号の8ロ(50%超100%未満のグループ内の合併としての適格合併の定義)及び法人税法施行令4条の3第3項2号(同一の者による支配関係の定義)となる。
これらの規定においては、合併対価として合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこと(法法2十二の8)、「同一の者」(法令4の3②二)による支配関係が継続することが見込まれていること(法令4の3③二・②二)、そして、被合併法人Aの従業者のおおむね80%以上が合併法人Bの業務に従事することと被合併法人Aの主要な事業が合併法人において引き続き営まれることの二つが見込まれていることが、適格合併となるための要件とされている。
イ 株式対価要件
法人税法2条12号の8の規定においては、「合併法人株式(省略)又は合併親法人株式(省略)のいずれか一方の株式(省略)以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(省略)として交付される金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの」という要件が適格合併の要件として示されている。
本件においては、合併対価としてPの株式のみが交付されるとのことであるため、この要件に該当することとなる。合併法人が合併対価として交付する合併親法人株式に関しては、税制上、合併法人がどのようにして取得したのかによって適格判定に影響を及ぼすこととはされていない。
ところで、合併親法人の株式を合併対価として交付する三角合併においては、合併法人の株式を交付する合併とは異なり、合併対価が合併法人の保有する合併親法人の株式の数に制限されることとなる。
合併法人が保有する合併親法人株式の数が合併対価として交付する数よりも多い場合には、合併法人は、相当の期間にその余った合併親法人株式を譲渡等によって処分すればよい(会135⑤)、ということになる。
他方、合併親法人が保有する合併親法人株式の数が合併対価として交付するべき株式の数よりも少ない場合には、合併法人は、合併親法人株式以外の資産を交付せざるを得ないこととなる。
上記の法人税法2条12号の8の規定においては、理由は明らかではないが、合併対価として合併法人の株式と合併親法人株式の双方を交付するものは適格合併とはしないこととされているため、合併親法人株式の数が合併対価として交付するべき数に足りているのか否かという点には、十分に注意をしておく必要がある。
ただし、合併法人が合併対価として交付するべき合併親法人株式の数に「一に満たない端数」が生ずる場合に関しては、法人税法65条(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定を根拠として平成20年度改正において創設された法人税法施行令139条の3の2(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)の規定に特例が設けられている(注)。
(注)法人税法65条の規定は、法人税法第2編第1章(各事業年度の所得に対する法人税)
の定めであって、「第二款から前款まで(所得の金額の計算)に定めるもののほか、各
事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。」とするものであり
、組織再編成が適格であるのか否かを定める第1編(通則)の取扱いについて定めるも
のではないため、本来は、法人税法施行令139条の3の2の規定の如何によって組織再編成の適格判定が変わることはない。
三角合併における合併親法人株式に「一に満たない端数」が生ずる場合の適格判定に関する取扱いを設ける場合には、本来は、法人税法2条12号の8の「適格合併」の定義中若しくはその委任政令に定めを設けるか、または、法人税基本通達1-4-2(合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定)のように法人税法2条の定義規定の解釈として記載する必要がある。
ただし、本稿においては、法人税法施行令139条の3の2に合併親法人株式の「一に満たない端数」の定めを設けた立法意図を考慮して、見解を述べることとしている。
この法人税法施行令139条の3の2第1項においては、合併親法人株式の数に「一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるとき」は、その端数に相当する部分は合併親法人株式に含まれるものとして、合併法人、被合併法人、被合併法人の株主の所得の金額を計算する、と定めている。
このため、合併親法人株式の数の「一に満たない端数」に相当する部分に関しては、金銭を交付しても、そのことをもって三角合併が非適格合併とされることはないこととなる(注)。
(注)三角合併は、会社法749条1項2号(株式会社が存続する吸収合併契約)の規定において合併法人株式以外の資産を合併対価として交付することが出来ることとされたことによって可能となったわけであるが、合併等の対価として合併法人株式以外の資産が交付されるという場面を想定すると分かるとおり、その資産に「一に満たない端数」があるという考え方は存在せず、会社法234条1項(一に満たない端数の処理)の規定においても、合併親法人株式の端数に関する定めは存在していない。三角合併において合併親法人株式の数の「一に満たない端数」に相当する部分について金銭の交付があったとしても、それは、会社法234条1項の「一に満たない端数」の処理には該当しないわけである。
このため、上記の法人税法施行令139条の3の2においては、法制度において存在しない合併親法人株式の数の「一に満たない端数」という概念が実際には存在するという前提に立って規定が設けられているということを認識した上で、実務に当たっては、法制度の如何とは別に、事実として、「合併親法人株式の数の一に満たない端数」が存在するということを明確にしておくことに留意する必要がある。
ロ 支配関係継続要件
本件においては、甲とその親族がHとPのそれぞれの株式の50%超を保有しているということであるが、「同一の者」が50%超の株式を保有しているわけではないため、法令の規定の文言どおりに解するとすれば、法人税法施行令4条の3第3項2号の規定において読み替える同条2項2号の規定の「同一の者」が被合併法人と合併法人の株式の50%超を継続保有することが見込まれることという要件に該当しないこととなる。
しかし、この法人税法施行令4条の3第2項2号の規定は、その文言に拘らず、「同一の者による完全支配関係」(同号を法人税法施行令4条の3第3項2号の規定によって読み替えた場合には「同一の者による支配関係」)という表現の全体が親族等を含む関係となっていると解釈する必要があると考えられる。
この詳細に関しては、著者他『詳解 グループ法人税制』(法令出版)の問18の解説を参照されたい。
ハ 従業者引継要件
法人税法2条12号の8ロ(1)においては、次のような要件が定められている。
「(1)当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(省略)」
本件においては、合併によって被合併法人であるAの全ての従業者が合併法人であるBに引き継がれるとのことであり、この要件に該当することとなる。
ニ 主要事業継続要件
法人税法2条12号の8ロ(2)においては、次のような要件が定められている。
「(2)当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(省略)」
本件においては、合併によって被合併法人であるAの全ての事業が合併法人であるBに引き継がれるとのことであり、この要件に該当することとなる。
上記イから二までに述べたとおり、本件の三角合併は、適格合併となるものと考えられる。
以下、本件の三角合併が適格合併となるという前提に立ち、被合併法人A、合併法人B及び被合併法人の株主Hの税制上の取扱いについて検討を行うこととする。
③ 被合併法人・合併法人及び被合併法人の株主の取扱いの検討
イ 被合併法人
適格合併の場合の被合併法人における取扱いに関しては、法人税法62条の2(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に定められている。
法人税法62条の2第1項においては、「当該合併法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る最後事業年度終了の時の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたもの」とすることとされている。
そして、この「政令で定める金額」に関して、法人税法施行令123条の3第1項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)においては、「適格合併に係る合併法人に移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る(省略)最後事業年度終了の時の帳簿価額(省略)とする」とされている。
ところで、これらの規定は、いずれも合併によって交付することとなる合併親法人株式に関しては、合併法人が取得して保有しているものを合併人の株主に交付するという前提で定められている。
このため、本件のように、被合併法人が合併親法人株式を保有しているという場合には、税制上、合併親法人株式が合併によって合併法人に移転すると考えるべきか否か、また、上記算式中の「適格合併の直前の帳簿価額」はいずれの法人のいずれの時点の金額と解釈してよいのか、というような疑問が生じてくることとなる。
これらの点に関しては、合併対価の額が被合併法人の保有する合併親法人の株式を資産に含めて評価した金額とされることとなることを考慮すると、被合併法人が保有している合併親法人株式が他の資産と同様に合併法人に移転し、その後、その合併親法人株式が合併対価として被合併法人に交付され、直ちに、被合併法人の株主に交付される、とするのが適当と考えられる。
このように考えるとすれば、被合併法人においては、最後事業年度終了の時の資産及び負債と資本金等の額を合併法人に引き継ぎ、一旦、合併法人に引き継いだ合併親法人株式を合併対価として取得する、という処理を行うこととなる。この場合の被合併法人における合併親法人株式の取得価額は、資産及び負債と資本金等の額の貸借差額、すなわち、利益積立金額と同額となる。そして、被合併法人は、その後、直ちに、その合併親法人株式を株主に交付することとなるが、この処理は、必然的に、利益積立金額を減少させて行うこととならざるを得ない。
<参考>
平成22年度改正前は、被合併法人が適格合併によって合併法人に引き継ぐものは、その資産及び負債と利益積立金額とされていた。このため、被合併法人が合併法人から交付を受けた合併対価をその株主に交付する処理は、株主からの出資額を示す資本金等の額を減少させて行うものとされており、株主においても、みなし配当は発生しないこととされていた。
しかし、平成22年度改正において、被合併法人が適格合併によって合併法人に引き継ぐものは、その資産及び負債と資本金等の額とされた。その結果、被合併法人が合併法人から交付を受けた合併対価をその株主に交付する処理は、利益積立金額を減少させて行うものとせざるを得なくなっているが、株主においては、従前どおり、みなし配当は発生しないものとされており、被合併法人と株主の処理を整合的に説明することが難しくなっている。
これらに関しては、著者他『詳解 グループ法人税制』(法令出版)の問115・116及び鼎談の677~680頁を参照されたい。
上記の処理のうち、資本金等の額の合併法人への引継ぎに伴う減少と株主に対して合併対価を交付する際の利益積立金額の減少に関しては、合併によって被合併法人が消滅することから規定を設ける意義がないため、特にそれらの根拠となる定めは設けられておらず、また、合併対価を取得して株主に交付したものとする処理に関しては、その根拠となる規定(旧法法62の2②)が平成22年度改正によって削除されており、根拠法令として示すことができる規定がないため、当然の解釈と説明する他ない。
また、合併対価として交付する合併親法人株式の数に「一に満たない端数」が生じ、その端数に相当する金銭が合併対価として交付されることとなることがあるため、その処理についても、確認を行っておく必要がある。
法人税法施行令139条の3の2第1項においては、この端数に相当する金銭の交付が行われる場合には、「当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式等に含まれるものとして、当該合併法人、当該被合併法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算するものとする」としている。
この「当該端数に相当する部分」は、株式ではなく、金銭で授受されるため、「当該合併親法人株式等に含まれるもの」とする処理がどのようなものを指すのか明確ではないが、合併法人の取扱いや被合併法人の株主の取扱いから推測すると、被合併法人は合併対価として端数を含めて合併親法人株式を受け取ったものとして合併の処理を行うことを求めたものと解される。
適格合併の場合に被合併法人が合併法人の株式又は合併親法人株式を合併法人から取得して直ちに株主に交付したものとする旨を規定していた旧法人税法62条の2第2項の規定は、既に述べたとおり、平成22年度改正によって削除されているが、法人税法施行令139条の3の2の規定が創設された平成20年度改正の時点においては、旧法人税法62条の2第2項の規定において合併親法人株式の取得価額とされていた金額は「純資産価額に相当する金額」(法令123の3②)とされており、合併親法人株式の取得と交付に関する取扱いは、合併対価として端数を含めて合併親法人株式を受け取ったものとして処理を行うという上記の解釈と整合性のある状態となっていた。
ただし、被合併法人がそのような処理を行うということになれば、現に交付される「一に満たない端数」に相当する金銭をどのように処理するのかということが問題となる。
この金銭に関しては、後に述べるとおり、被合併法人の株主においては、「一に満たない端数」の合併親法人株式の譲渡対価の額と解するほかないため、被合併法人においては、「仮受金」の発生と清算とするか、または、処理自体を行わないこととするかのいずれかとするのが適当と考えられる。
ロ 合併法人
適格合併の場合の合併法人における資産及び負債の取扱いに関しては、法人税法62条の2及び法人税法施行令123条の3第4項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の引継価額等)に定められている。
法人税法施行令123条の3第4項においては、合併法人は適格合併により被合併法人の最後事業年度終了の時の帳簿価額によって資産及び負債の引継ぎを受けたものとする、とされている。
このため、本件においては、Bは、Aの最後事業年度終了の時の資産及び負債について、その時の帳簿価額によって引継ぎを受けたものとすることとなる。
これらの規定においては、合併対価となる合併親法人株式について、被合併法人から引継ぎを受けることとなる場合の特別な定めは設けられておらず、また、そのような場合に特に問題が生ずることも想定されない。
ただし、三角合併の場合には、合併法人においては、合併親法人株式を被合併法人に交付することとなるため、合併親法人株式の譲渡の処理をどのように行うのかという問題が生ずることとなる。
これに関しては、法人税法61条の2第6項において、譲渡対価の額を「適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額」とすることとされている。
上記イにおいても述べたとおり、この規定も、合併によって交付することとなる合併親法人株式に関しては、合併法人が取得して保有しているものを被合併法人の株主に交付するという前提で定められている。
このため、本件のような場合には、合併法人は、「適格合併の直前」には合併親法人株式を保有していないため、「適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額」をどのような金額と解するのかということが問題となる。
これに関しては、被合併法人が合併親法人株式を合併法人に引き継ぎ、その合併親法人株式が被合併法人に交付されると考えるとすれば、この「適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額」は、合併親法人株式の交付の処理をする直前のその帳簿価額に相当する金額、すなわち、「被合併法人から引継ぎを受けた合併親法人株式のその引継ぎを受けた時の帳簿価額に相当する金額」と解するのが適当と考えられる。
合併法人が適格合併に際して増加させることとなる資本金等の額については、法人税法施行令8条1項5号(合併において合併法人が増加させる資本金等の額)において次の計算式によって示す金額を増加(マイナスの場合には、減少)させることとされている。
被合併法人の最後事業年度終了の時の資本金等の額
- 被合併法人の株主等に交付した合併親法人株式のその適格合併の直前の帳簿価額
この規定も、合併によって交付することとなる合併親法人株式に関しては、合併法人が取得して保有しているものを被合併法人の株主に交付するという前提で定められている。
このため、上記計算式の「被合併法人の株主等に交付した合併親法人株式のその適格合併の直前の帳簿価額」は、規定上、合併法人における金額と解さざるを得ない。
このような場合には、この「被合併法人の株主等に交付した合併親法人株式のその適格合併の直前の帳簿価額」はない、という解釈も採り得ないわけではないが、被合併法人が合併親法人株式を合併法人に引き継ぎ、その合併親法人株式が被合併法人に交付されると考えるとすれば、この金額は、合併親法人株式の交付の処理をする直前のその帳簿価額、すなわち、「被合併法人から引継ぎを受けた合併親法人株式のその引継ぎを受けた時の帳簿価額」と解するのが適当と考えられる。
合併法人が適格合併に際して増加させることとなる利益積立金額については、法人税法施行令9条1項2号(合併において合併法人が増加させる利益積立金額)において、次の計算式によって示す金額を増加(マイナスの場合には、減少)させることとされている。
被合併法人の最後事業年度終了の時の資産の帳簿価額
-(被合併法人の最後事業年度終了の時の負債の帳簿価額 + 増加した資本金等の額 + 合併親法人株式の適格合併の直前の帳簿価額
+ 抱合株式の適格合併の直前の帳簿価額)
上記の計算式中の「合併親法人株式の適格合併の直前の帳簿価額」に関しては、上記の資本金等の額に関する説明の中で述べたところと同じ理由により、「被合併法人から引継ぎを受けた合併親法人株式のその引継ぎを受けた時の帳簿価額」と解するのが適当と考えられる。この利益積立金額の増加額(上記計算式の金額がマイナスの場合には、減少額)は、平成22年度改正以後は、被合併法人の利益積立金額を引き継いだものではなく、適格合併に伴って合併法人において新たに発生するものとされている。
また、合併対価として交付する合併親法人株式の数に「一に満たない端数」が生じ、その端数に相当する金銭を合併対価として交付することとなることがあるため、その処理についても、確認を行っておく必要がある。
法人税法施行令139条の3の2第1項においては、この端数に相当する金銭の交付を行う場合には、「当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式等に含まれるものとして、当該合併法人、当該被合併法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算するものとする」としている。
このため、合併法人が合併対価として交付する合併親法人株式は、「一に満たない端数」を含めたところで交付の処理を行うこととなる。
合併対価として交付する合併親法人株式の取扱いについて定めた法人税法61条の2第6項の規定においては、同条1項1号の譲渡対価の額を「当該合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とするとしてるため、実際には「一に満たない端数」の合併親法人株式を交付することはないが、合併親法人株式の交付の処理を行う場合のその金額は、「一に満たない端数」の帳簿価額に相当する金額を含めた金額とすることとなる。
合併法人がこの「一に満たない端数」に相当する数又はそれ以上の数の合併親法人株式を保有している場合には、この帳簿価額に相当する金額を計算することは容易であるが、合併法人はこの「一に満たない端数」に相当する数の合併親法人株式を保有していないこともあり得る。
このような場合には、上記の処理をどのように行うべきかという問題が生ずることとなるが、このような合併法人が保有していない「一に満たない端数」の合併親法人株式に関しては、有価証券の空売りに係る規定である法人税法施行令119条の10(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)の規定の中に平成20年度改正において新たに2項以下の規定を設けて、合併法人が保有していない「一に満たない端数」の合併親法人株式の上記の交付(譲渡)を「有価証券の空売り」の「売付け」と、「一に満たない端数」に相当する金銭の交付を「買戻し」とみなすこととし、合併法人が「一に満たない端数」の合併親法人株式を保有していない場合であっても、その「一に満たない端数」の合併親法人株式に相当する部分の処理を法人税において意図する結果となるようにすることができるようにしている(注)。
(注)合併親法人株式に関しては、会社法234条1項の規定の適用はなく、合併法人株式のように、「一に満たない端数」がある場合に競売等を行ってその代金を株主に交付しなければならないという制限があるわけではないため、合併法人が保有していない「一に満たない端数」の合併親法人株式に関して「有価証券の空売りを行ったものとみなして、同項(法人税法61条の2第19項 著者注)の規定を適用する」(法令119の10②)とすることにも、一定の理由はあると考えられる。
ただし、この合併法人が保有していない「一に満たない端数」の合併親法人株式に関しては、例えば「取得し、直ちに交付したものとする」というように、その合併の際の処理の仕方を定めることが求められるわけであり、その処理を「有価証券の空売り」という金融取引とみなすことが適切であるのか否かという点には、異見があるものと考えられる。
具体的には、法人税法施行令119条の10第2項の規定において、合併法人が保有していない「一に満たない端数」の合併親法人株式の譲渡対価の額は、一株当たりの合併親法人株式の帳簿価額にその保有していない「一に満たない端数」の合併親法人株式の数を乗じた金額とし、譲渡原価の額は、交付する金銭の額とし、買戻しによって譲渡利益額又は譲渡損失額を計上する日は、合併の日とされている。
ハ 被合併法人の株主
被合併法人の株主においては、合併が適格合併であり、合併親法人株式のみが交付される場合には、みなし配当が生ずることはなく、被合併法人の株式を帳簿価額によって譲渡し、合併親法人株式をその帳簿価額によって取得したものとすることとなる。
具体的には、法人税法61条の2第2項において、「旧株」(被合併法人の株式)の譲渡対価とする金額を合併の「直前の帳簿価額に相当する金額」とすることによって譲渡損益が生じないようにするとともに、法人税法施行令119条1項5号において、合併親法人株式の取得価額を「被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額((省略)当該親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額)」としている。
本件においては、Hは、Aの株式をその帳簿価額によって譲渡してPの株式を取得したという処理を行うのみということになる。
ただし、合併対価として交付するPの株式の数に「一に満たない端数」が生じ、その「一に満たない端数」に相当する金銭を合併対価として交付することとなる場合には、その「一に満たない端数」の株式について、譲渡の処理を行い、譲渡利益額又は譲渡損失額の計上を行う必要がある。